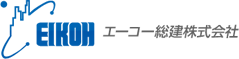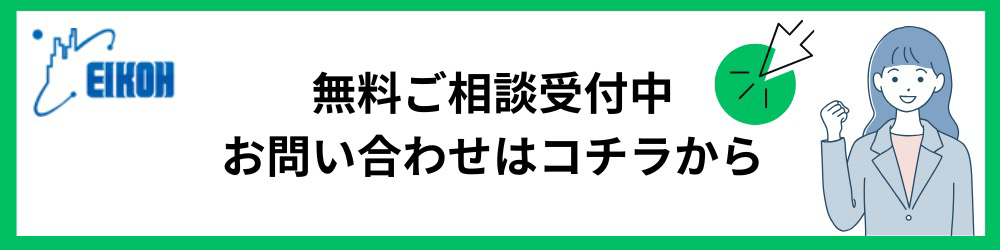COLUMNコラム
- EIKOH エーコー総建株式会社[HOME]
- コラム一覧
- 大規模修繕には補助金活用を!マンション管理に必要な制度や注意すべき失敗例を徹底解説
2025/04/28大規模修繕には補助金活用を!マンション管理に必要な制度や注意すべき失敗例を徹底解説
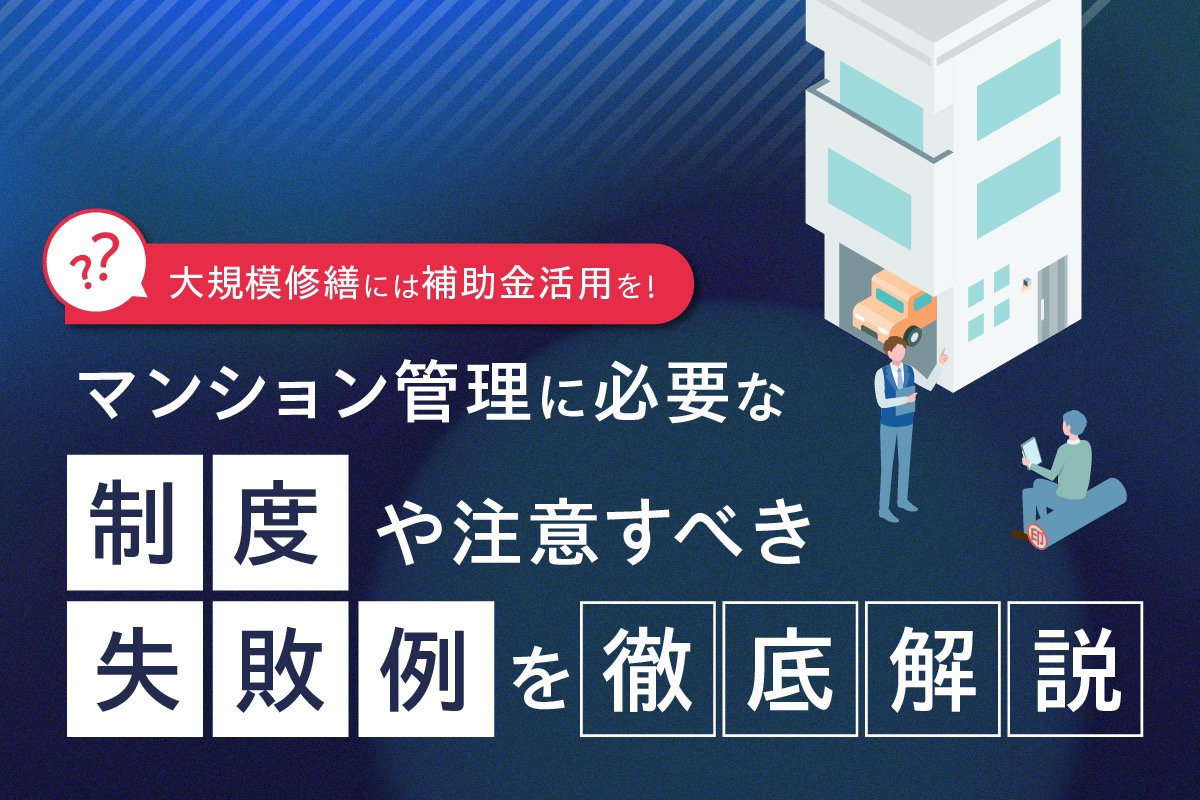
マンションを安全かつ資産価値のある状態に維持するために、周期ごとの大規模修繕は欠かせません。
ですが、大規模修繕工事を行うには膨大な費用が掛かります。
一度の大規模修繕で予算オーバーが起こってしまうと、修繕積立金の値上げ・マンションの組合員からの一時金徴収などの負担が増えてしまいます。
それらを回避するために押さえておきたいのが補助金や助成金です。
この記事では、マンションの大規模修繕に利用できる補助金・助成金についての解説や、補助金申請までの流れ、補助金以外の支援制度などについて解説します。
合わせて、東京のマンションの大規模修繕を手掛けて50年の私どもエーコー総建に関してもご紹介しています!
マンションのオーナー様で大規模修繕の費用を抑えたい、補助金や助成金を活用してより良い改修工事を行いたいという方はぜひ最後までご覧くださいね。
大規模修繕に使える補助金・助成金とは
大規模修繕に利用できる補助金や助成金とは、どういったものでしょうか。
この二つは似ているようで異なる制度です。
違いを知らないとせっかく申請をしても認可が下りず支援が受けられないということも。また、マンションのある自治体や状況によっても受けられる内容が違うため、しっかりと条件を確認し注意することが必要です。
補助金と助成金の違い
補助金も助成金も対象者にお金が支給されるという点は同じですが、意味合いや条件が異なります。
大きな違いは以下の通りです。
・補助金・・・一定の条件を満たし応募した申請者を審査し、基準を満たしている者の中からさらに選ばれた一部の申請者に給付されるもの。特定の事業や活動に対して国や地方自治体から支給される。
・助成金・・・それぞれの制度に条件があり、これを満たしていれは誰でも給付されるもの。補助金よりもより広範囲な支援を目的としているため補助金よりも受けやすい。上限金額があり、支給金額がそこへ到達すると早期終了になることもある。
補助金が必要な理由
大規模修繕において、その時受けられる補助金があるかとうかを確認することはとても大切です。
支援があるかどうかで組合員一人当たりにかかる金額がかわるため、組合員の心理的負担や実際の支払いを減らすしとができ、その後の関係を良好に保つことが可能です。
支援を受けずに大規模修繕を行ったため、1区画につき50万円の負担金が発生したという事例もあります。
年度ごとに特別な補助事業があることも多いため、大規模修繕をする際には必ず対象になる補助金がないか確認しましょう。
マンション大規模修繕で利用できる主な補助金
では実際にマンションの大規模修繕で利用できる補助金とはどのようなものでしょうか。
・劣化診断補助金
・耐震改修補助金
・アスベスト除去補助金
・バリアフリー補助金
それぞれについて詳しく解説します。
劣化診断補助金
劣化診断補助金(劣化診断補助事業)とは、大規模修繕を実施する前や長期修繕計画の見直しなどのタイミングで行う「マンションの劣化診断」のためにかかる費用に対する補助金です。
劣化診断とは、マンションを専門家が実際に調査し、表面からは気づかない内部の破損や設備の劣化を診断することです。
国土交通省が提示する「マンションストック長寿命化等モデル事業」資料における「劣化診断費補助金」では、条件を満たすと一案件当たり原則年間500万(最大3年)を限度とした補助が行われます。
住宅部分だけでなく、非住宅部分を含む建築物(複合建築物)も対象になるため、店舗や事務所とマンションが複合した物件をお持ちのオーナー様もぜひチェックしてみてください。大規模修繕の費用削減に今すぐ直結する補助金ではありませんが、劣化診断はすべての改修工事の基本となりますので是非補助を受けて診断をお勧めします。
ただし、この補助金は直接経費(賃金・旅費・備品購入費・委託料等)が対象であり、以下に挙げる経費は補助対象とならないため注意が必要です。
・事業提案された住宅または施設以外の建物等施設の建設や不動産取得に関する経費
・国内外を問わず学会出席のための旅費・参加費等
・補助事業の実施中に発生した事故や災害の処理のための経費
・その他補助事業に関連しない経費
さらに詳細が気になる方は国土交通省の資料「マンションストック長寿命化等モデル事業1をご覧ください。
耐震改修補助金
酎震改修補助金は、地震による被害を軽減するために必要な耐震診断・耐震工事などの大規模修繕を行う際に利用できる補助金です。
特に昭和56年以前に旧耐震基準で建てられているマンションなどの建築物は、適正な耐震化を行うために整備・改修が必要です。
耐震強度を更新することで、その後の大規模修繕の頻度や劣化・破損個所を減らし、居住者の安全を守るとともに修繕積立金などの負担軽減にもなります。
地震災害の多い日本において耐震改修は押さえておくべきポイントです。
この酎震改修補助金は国主導ではなく各自治体で行われている補助金の為、気になるオーナー様は各自治体のホームージをチェックしてみましょう。
アスベスト除去補助金
アスベスト(石綿)とはマンションなどの建築物の耐火性・断熱性・防音性・防水性・絶縁性を高めるために建築材料として使用されてきました。
しかし、吹付時や解体時に飛散したものを吸うことで肺がんなどの健康被害につながる恐れがあることから現在では使用が禁止されています。
禁止以前に「吹付アスベスト」や「アスベスト含有吹付ロックウール」が使用された建築物から、居住者の安全を守り、安心して暮らしてもらうためにアスベストを取り除く修繕工事に使える補助金が、アスベスト除去補助金です。
アスベスト除去補助金には3つの主導制度があります。
・国土交通省「建築物アスベスト改修事業」
・厚生労働省「石綿障害予防対策費補助金」
・各自治体によるアスベスト除去補助金
民間の建物の場合は国から地方自治体を経由して補助を行うと指針が出ているため、これをご覧いただいているマンションオーナーの皆様は各地方自治体の補助金制度をご確認ください。
また、アスベスト除去工事の際にはアスベスト含有部分を水でふやかしたり、飛散しないよう水をかけながら取り除いたりします。
バリアフリー整備助成
マンションの住みやすさを向上させるための大規模修繕工事や改修工事に使える助成金がバリアフリー整備助成です。
主に共用部分(敷地内の道路・駐車場・廊下・階段・エレベーターなど)の修繕や今までなかった場所への手すりの設置、段差をなくして車いすが通れるスロープやエレベーターを設置するなどの機能改善が対象になります。
時代とともに建物に不備が出てくることはもちろんですが、マンションの居住者の高齢化が進むためバリアフリー化は急務と言えます。
まずは無料見積もりを出してくれる地域の業者に複数依頼して、現在のマンションにどんなバリアフリー化をするのか見極めることが大切です。
補助金・助成金を探し出すための効率的な方法
補助金・助成金が色々とあるのはご理解いただけたかと思いますが、その中から最適な補助金・助成金はどうやって選び、申請すればいいのでしょうか。
情報は必ず公式サイトへ
まずは利用すべき情報源を「公式なもの」に限定することです。
「••補助金」と検索すると一覧でまとめられた個人サイトや企業のページが出てきますが、その情報は古くなっている可能性もあるため最終的には自治体や国の公式ホームページを確認することができます。
ですが、関連する団体やNPOなどの資料を見て知識をつけることも大切なので、しっかりと情報を集めて活用し、その内容に適した公式の案内をチェックして申請しましょう。
自治体のウェブサイトはサイトマップでチェック
耐震改修やアスベスト除去、共有部分のバリアフリー化や省エネ化を目指す場合は地方自治体のウェブサイトを確認することも大切です。
地方自治体のホームページには地域のためのあらゆる情報が掲載されており、内容を全て確認すると時間がかかるため、ホームページの「サイトマップ」という機能を使いましょう。
サイトマップとはウェブサイトの構造や内容を一覧で示す地図のようなもので、そこからキーワードを見つけることで欲しい情報に迅速にアクセスすることが可能です。
大規模修繕をする際に補助金を受けたいけど、調べてもよくわからない…というオーナー様もいらっしゃるでしょう。
そんな時はプロに効くのが一番です!
ぜひ私どもエーコー総建株式会社に一度ご相談ください。
マンションやビルを建てるのではなく「修繕する」ことに特化したエキスパートたちが、オーナー様のお悩みに寄り添います。
補助金申請の流れと必要書類
マンション大規模修繕の際の補助金申請の流れはどのようなものでしょうか。
申請のステップと申請書類について解説します。
申請の準備ステップ
補助金の申請は大きく分けて6つのステップにわかれます。
①業者に見積もりを依頼
大規模修繕や改修を行ってもらう業者に、事前にマンションの状況確認と見積もりを依頼する。
補助金の対象になるための工事や設備の項目が入るよう事前に相談すると、適切なアドバイスがもらえることも。
②見積書をもとに補助金制度を調べる
見積書をもとに国や自治体のホームページで補助金や助成金の要項を再度調べ、当てはまっていることを確認。
例えば共用部分のリフォームに階段が含まれているかなど、詳しく項目を確認することが大切。
③業者との契約前に必要書類を用意し国や自治体に申請
補助金や助成金を申請するために必要な書類を作成して、国や自治体に申請。
補助金の交付が決定したら「補助金交付決定通知書」が届くため、それを確認してからの契約がおすすめ。
④申請が通ったら工事に着工
契約が完了したら事前に用意した「事業計画書」の通りに工事に着工する。
これを遵守しないと補助金の交付に影響する可能性あり。
⑤実績報告書など交付に必要な書類を国や自治体に提出
工事が終了したら、「実績報告書」や指定された書類の提出を行う。
申請時の書類とともに確認され、適切な工事だったかを審査される。
⑤補助金の金額が決定され振り込まれる
審査の結果補助金額が決定し、指定した口座に補助金が振り込まれる。
申請書類のポイント
補助金の決定には正確な申請書類を用意することが何よりも大切です。
特に工事の対象となる共用部分の内容は、参考資料などを添付して正確に記載しましょう。必要な要件が漏れないように、書類の形式や目次・概要もきちんと確認し、書類に適切な内容がまとめられているかで補助金の審査がスムーズに進む可能性が高まります。